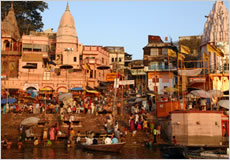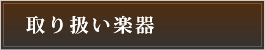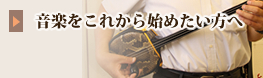タブラはしゃべる太鼓といわれ、手のひらと指でたたきリズムだけでなく、メロディーを奏でる事ができる小さな太鼓二つで一組の打楽器です。高音のタブラは木製、低音のパヤは金属でできており、両方とも上面の片側がくりぬかれ、ヤギの皮がはられ、革製のストラップで締めらています。
この宗教の行事をもとに産まれたインド音楽は、その後、イスラム教の流入など、宗教と密接に関わりながら、理論、技術が発達していき、西洋の音楽とは全く異なる音色を奏でるようになったのです。
奏者は、手のひらと指を駆使し、右手で高音のタブラ、左手で低音のバヤをたたくことで、多彩な表現を行ない、タブラ(バヤ)が奏でる音は、ボールと呼ばれる固有の名前がついています。奏者は、ボールを使い、音色の組み合わせを記憶し、様々なリズム、メロディーを奏でるのです。
記憶し、様々なリズム、メロディーを奏でるというように、北インドの音楽は、即興音楽であり、楽譜を使いません。奏者は聴衆とともに、独自のルールに基づき、その場で曲を作って行きます。このような北インドの音楽は、紀元前数世紀には、文献として記録されており、その紀源は、バラモン教(ヒンドゥー教の原型)教典の読踊に遡るといわれています。この宗教の行事をもとに産まれたインド音楽は、その後、イスラム教の流入など、宗教と密接に関わりながら、理論、技術が発達していき、西洋の音楽とは全く異なる音色を奏でるようになったのです。