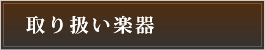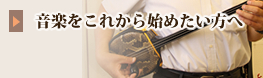中国の民族楽器は、「吹奏楽器(管楽器)」「打楽器」「つま弾く弦楽器」「弓で引く弦楽器」の4種類に大きくわけられます。それぞれの楽器が奏でる音色には個性があり、その背景には歴史があります。本頁では、国際楽器が取り扱う、弓で引く弦楽器、二胡と馬頭琴をご紹介しましょう。
二胡が奏でる音色は人間の声に近く、演奏する人により音色が違うので、自分だけのオリジナルの音色を作る事ができます。二胡が産まれたのは、映画や、小説に取り上げられる事が多い三国志演義に綴られる三国志の時代から約700年後の宋の時代です。この時代では、二胡は、「奚琴」(けいきん)と呼ばれ、竹の棹、竹のスティックで擦るという楽器で、軍隊の間で流行もしていたという文献も残っています。明代末、清代(1644-1912)に、各地方劇と大衆芸能の発展に伴い、伴奏として使われるようになるにつれ、中国全土に広がりを見せます。今日では、独奏曲も数多く作曲されると共に、民族音楽だけでなくクラシックやポピュラー音楽にも演奏されるようになっています。
二胡が奏でる音色は人間の声に近く、演奏する人により音色が違うので、自分だけのオリジナルの音色を作る事ができます。二胡が産まれたのは、映画や、小説に取り上げられる事が多い三国志演義に綴られる三国志の時代から約700年後の宋の時代です。この時代では、二胡は、「奚琴」(けいきん)と呼ばれ、竹の棹、竹のスティックで擦るという楽器で、軍隊の間で流行もしていたという文献も残っています。明代末、清代(1644-1912)に、各地方劇と大衆芸能の発展に伴い、伴奏として使われるようになるにつれ、中国全土に広がりを見せます。今日では、独奏曲も数多く作曲されると共に、民族音楽だけでなくクラシックやポピュラー音楽にも演奏されるようになっています。
【参考:日本二胡振興会】


日本では、「スーホの白い馬」という少年スーホと白い馬の絆を通じ、生まれる馬頭琴に関する物語で初めて馬頭琴を知った人も多いのではないでしょうか。馬頭琴の名は棹の先端にある馬の頭の彫刻から名付けられています。モンゴルの遊牧民の間に古くから伝わる楽器で、2000年以上の歴史があり、馬頭琴を弾くとその家に幸いが訪れるといわれています。このモンゴル民族を代表する楽器は、伴奏だけでなく独奏曲も増え、新たな可能性を探る試みが様々なところで行われています。